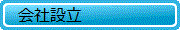相続が心配な方へ、相続でお困りの方へ
相続は、親、子、兄弟など肉親の突然の死亡から開始し、
通夜、葬儀などの行事が立て込み、相続開始から
相続税の申告期限までの期間は、精神的にも物理的にも
短いものです。その為、相続税の申告手続は、
できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに
円滑に進めていきましょう
相続が心配な方は、生前中に現時点での
相続税のシュミレーションを行うことをお勧めします。
自分の財産を専門家に評価してもらい、
認識しておくことで、納税資金準備に繋がります。
相続が発生してから、納税資金がないと、
相続人に負担を残してしまいます。
納税資金準備の為にも、相続税のシュミレーションを
検討してみてはいかがでしょうか?
相続人に遺産相続の争いを起こさせないためにも
遺言書の作成をお勧めします。
遺言書がある事により、相続人が被相続人の意思を尊重し
相続のトラブルを回避できるケースがあります。
相続が発生したら、誰に相談したらいいのでしょう。。。
相続税については税理士、
登記関係は司法書士、行政書士
遺産分割が整わず裁判になれば、弁護士
各種の専門家の知識が必要になります。
上間智志税理士事務所では、ワンストップで、
司法書士、行政書士、弁護士と連携して
相続手続を進めていきます

主な手続の期限
相続の承認、放棄
限定承認 … 相続財産の範囲において被相続人の債務及び遺
贈の義務を負担します。
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
相続人が複数いるときには、全員が共同して
のみこれをすることができます。
これに対して
単純承認 … 相続財産・債務を全面的に承継します。
従って、相続財産をもって相続債務を弁済し
きれない場合は、相続人は自己の個人財産によ
り弁済しなければなりません。
以下の自由が生じた場合は、単純承認をした
ものとみなされます。
相続財産の全部又は一部の処分
熟慮期間(3ヶ月)内に限定承認又は放棄を
しなかったとき
背信的行為(限定承認又は放棄をした後、相
続財産の全部又は一部を隠匿、消費したとき
放棄 … 相続の放棄により、はじめから相続人とならなかっ
たものとみなされます。
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
所得税の準確定申告
準確定申告 … 被相続人の死亡年の1月1日から死亡日まで
の所得を確定申告する。(確定申告義務がある
場合のみ)
死亡した者の相続人は、準確定申告書を、相
続の開始があったことを知った日の翌日から4
ヶ月以内に、被相続人の納税地の所轄税務署長
に提出。
相続税の申告
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
上間税理士事務所が解決します!!